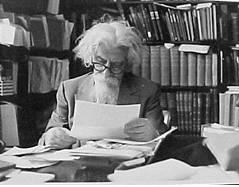
アブラハム・ヨシュア・ヘシェルと ハシディズム
Abraham Joshua Heschel and Hasidism
手島佑郎 Jacob Yuroh Teshima gilboa@ma.0038.net
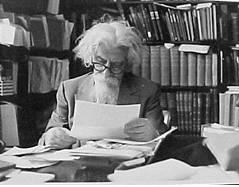
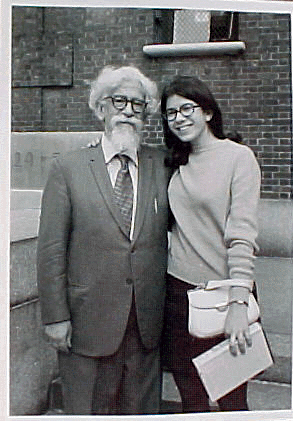
1. はじめに: ヘシェル、その足跡
現代の米国宗教界に最も大きな影響を与えている人物の一人といえば、ユダヤ教を代表するアブラハム・ヨシュア・ヘシェル(1907-1972)の名をあげねばなるまい。
彼は1907年1月11日、ポーランドのワルシャワに生まれた。長じて1928年にベルリン大学に進む。
1935年に学位取得後、マルチン・ブーバーが所長をつとめる「ユダヤ人成人教育センター」で講師をつとめる。37年パレスチナに移住するブーバーは、ヘシェルを後任に指名したが、翌年ヘシェルもナチスのユダヤ人排斥を逃れてロンドンに移り、40年春米国に到着する。
40~45年、シンシナティのヘブル・ユニオン・カレッジ(略称HUC)で教え、45年秋から没する72年までニューヨークのアメリカ・ユダヤ神学校(The Jewsih Thological Seminary of America 、略称JTS)で教えた。
1951年に彼の2冊目の著書Man Is Not Aloneが世に出るや、キリスト教プロテスタント神学界の泰斗ラインホルド・ニーバーはこれを激賞し、一躍ヘシェルの存在は人々に知られることとなった。
学者としての彼の活動領域はラビ学、聖書学、神学、哲学、倫理学と広範囲にわたっている。
ラビ学の分野ではMaimonidesや、Theology of Ancient Judaism (Torah min hashamayim b'ispaklariah shel hadorot) が代表作である。後者はミシュナ、タルムードにおけるラビたちの対立見解を公平に紹介し
ながら、ユダヤ教神学の基礎を紹介した上下2巻の好著である。彼は第3巻の原稿をほぼ書き上げていたが、遺族の了解が得られず未だ出版されていない。
ヘブライ大学のエフライム・ウルバッハはラビ思想をテーマ毎にまとめたThe Sages, Their Concepts and Belif (Hazal -Pirkei emunot v'de'ot) を著わしているが、それは、彼がヘシェルのTheology of Ancient Judaism に刺激された結果であった。
聖書学の分野では、彼の学位論文となったDie Prophetieを残している。これは英訳のペーパーバック本も出ており広く学生たちに読まれている。
神学分野の彼の主著は、上述のMan Is Not Alone とGod in Search of Man である。
The Insecurity of Freedom は、さまざまの講演原稿を収録したものである。これは彼の社会活動家としての側面を示す倫理思想書といってよい。
彼は教育関係者の前で講演することも多かった。最近では彼の教育思想を受け継いだ教育者たちが、ニューヨーク、シカゴ、ロスアンゼルなどに彼の名前を冠したユダヤ教の小学校網を展開している。
ヘシェルの特異性は、たんにユダヤ教の学者であったのにとどまらず、社会的正義にも強い関心をいだき、じっさいに身をもって行動で示したことである。その行動力が人々の、とりわけユダヤ教以外の人々の尊敬を招いた。
たとえば、カトリックのベア枢機卿からの信頼を得て、彼はユダヤ教を代表して1964年バチカンでパウロ6世と会見し、ユダヤ教とカトリック教会との和解の橋渡しをした。この結果、カトリック教会は第2回バチカン公会議で、ユダヤ人への伝道条項を取り下げた。
1963年に黒人公民権運動のキング牧師、アンドリュー・ヤング牧師らと出会ったことは、65年のアラバマ州セルマにおける大行進へと発展した。そればかりか、ベトナム反戦宗教家連合という運動結成の端緒ともなった。
65~66年にはブロードウェイをはさんでJTSの斜め向にあるキリスト教のユニオン神学校客員教授にユダヤ人として初めて招かれた。この陰にはニーバーやジョン・ベネットとの深い友情があった。
1972年12月17日だか18日のこと、ヘシェルはベトナム反戦活動のとがで収監されていたフィリップ・ベリガンとジミー・ホッファが釈放されるというので、大雪のなか刑務所まで出迎えにいった。寒さに凍えながら門前で数時間立ち尽くしていた。
当時、筆者はヘシェルの門下生であった。12月19日にニューヨークへ帰ってきたとき、彼は疲労しきった様子であった。
そして1972年12月23日安息日の未明、アブラハム・ヨシュア・ヘシェルは忽然とこの世を去った。その前日22日の午前中に、最後の著書 A Passion for Truth の原稿を書き上げ、出版社に渡していた。
2. ヘシェルの生い立ち
以上はヘシェルの活動の大雑把な概要である。その人物、博覧強記にして、その行動、多岐の社会活動にわたる。なぜ彼があのように行動的であったか。この疑問を解くためには、彼の生い立ちから知らねばならない。
彼はユダヤ教徒中のユダヤ教徒として育った。彼の父方の祖先は、ユダヤ教正統派のハシディズムの名門アプト・レベと呼ばれた初代ラビ・アブラハム・ヨシュア・ヘシェル(1748-1825)に遡る。
ハシディズムの世界では、卓越したラビが出ると、その周囲に一派が形成され、一門の最高指導者はレベ(Rebbe)と呼ばれる。たいていラビの住んでいた地名を冠して××レベと呼ぶ。
初代ヘシェルはガリチアのアプトに住んでいた。彼はハシディズムの開祖ラビ・イスラエル(1700-1760)、通称バアル・シェム・トブ(良き護符師)(1)から数えて第4世代の俊秀であった。困窮者をよく助け、別名オヘブ・イスラエルと呼ばれた。初代ヘシェルの曽孫がまたアブラハム・ヨシュア・ヘシェルと命名され、そのまた孫が本稿で取り上げているアブラハム・ヨシュア・ヘシェルである。ヘシェルは祖父の名前をもらったわけである。
この祖父の妻レアの祖先は、バアル・シェム・トブの跡を継いだハシディズム2代目の指導者ドブ・ベエル(1710-1772)、通称ハマギッド(説教者)にまで遡る。
ヘシェルは10歳のときに、父モシェ・モルデハイ(1873-1916)を失っている。少年時代のヘシェルの人格形成には、母リフカ(1874-1942)と母の兄アルター・イスラエル・ペルロウ(ノヴォミンスク・レベ 1847-1933)の影響が大きかった。
ノヴォミンスク・レベの助言で、10歳のヘシェルにベツァレル・レヴィという家庭教師がつけられ、父方の穏やかな学風とはちがって、鋭く問題提起をするコツク派の学風を仕込まれた。1
3歳で成人式を済ませると、新たに新進気鋭のラビ・メナヘム・ゼンバの下でラビ学の指導を受け、1916年頃にラビの資格を授与されている。
ちなみに母方の祖先は、ドブ・ベエルの弟子レヴィ・イツハク(1740-1810)にまで遡る。
父が亡くなったとき、門弟たちは既に成人式を済ませているヘシェルの兄ヤコブ(1903-1970)をではなく少年ヘシェルを自分たちのレベに仰ぎたいと申し出たが、母が断わった。これは、幼くしてヘシェルの人格や才能が光っていたことを物語るエピソードである。
ヘシェルがニューヨークに移ってからのことであるが、従兄で長姉サラの夫でもあったブルックリンに住むコピチニッツ・レベのアブラハム・ヨシュア・ヘシェル(1888-1967)は、再三ヘシェルにコピチニッツ派のレベに就任してほしいと要請した。しかし、ヘシェルはその要請を固く断わった。結局、甥のモーシェ(1927-1975)がレベを継承した。
ヘシェルは、保守派ユダヤ教のJTSの教授であったが、彼個人の生活においては正統派ハシディズムの伝統を最後まで厳格に守っていた。ヘシェルの自宅でパーティーがあると、ハシディズムの親戚たちも招かれていたし、彼もブルックリンの親戚たちを折々に訪ねていた。
3. ヘシェルと非ハシディズム社会
なぜヘシェルはハシディズム社会にとどまらずに世俗社会に出たのか。彼の経緯については、ヘシェルの弟子のひとり、エドワード・カプランが記した評伝『Abraham Joshua Heschel』(2)に詳しく描かれている。しかしながら、カプランの記述は、大半が断片的資料と第三者による仄聞との積み上げであって、ヘシェル自身の告白によるものではない。
筆者は1970年9月からJTSの彼のもとで学び、72年9月には彼の指導下で博士課程学生になることを許された。彼が研究室から自宅に帰るさいは、毎日ブロードウェイ122丁目角のJTSから、リバーサイドドライブ115丁目のアパートまで鞄持ちをした。
72年11月下旬であったと記憶しているが、ある日、思いきってヘシェルに尋ねた(3)。
「先生はなぜコピチニッツ派のレベにならなかったのですか」
彼は歩みをとめ、歩道の真ん中に立ち止まって、大きく息をついでから答えた。「聞きなさい。ミドラシュによれば、モーセがシナイ山で柴が燃えているのを見たとき、彼は(天の)宮殿が燃えているのも見た。彼は、なぜ誰も宮殿の火を消そうと駆けつけないのか怪訝に思った。そして彼は進んで火を消そうとした。 すると神が彼に語りかけた。『モーセよ、モーセよ、宮殿はわたしの責任のもとにある。これはわたしが面倒をみる。もしおまえがもう一つの宮殿の面倒をみてくれたら、わたしはどんなに嬉しいだろうか。その宮殿とは他でもない、おまえが住んでいる世界だ』と。 それ以来、モーセは神の共同者になったと、ミドラシュは教えている」
ヘシェルはまた大きく息をついだ。「わたしが若い頃にハシディズムの外の世界に出ていったのは、さしずめモーセが燃える柴を見にいったようなものだ。外の世界の学問とトーラーの真理とどう違うのか、自分で確かめたかったわけだ。
従兄がコピチニッツ派のレベになってくれと頼みに来たとき、このミドラシュを思い出したのだ。コピチニッツ派の者たちは神の導きの下にあるし、有能な人材が他にもいる。彼等に面倒をみさせればいい。だが、彼等以外のこの世界を、世界全体をだれが面倒みるべきか?
きみも知っているように、ユダヤ教には多くの貴重な宝がある。多くの教えとメッセージがある。それを外の世界はほとんど誰も知らない。
もしわたしがそれを外の世界に伝えないならば、ずっと宝は埋もれたままになる。わたしはハシディズムやユダヤ教全体が有している宝を外の世界の人々に伝え、外の世界のために尽くそうと決心したのだ。聖なる経験をした者は、行動を通して世界に役立たねばならない。それがわたしの使命だと思ったのだ。だから、コピチニッツ派のレベにならなかったのだよ」
この日、ヘシェルは話に夢中になってブロードウェイを112丁目の八百屋の角まで歩いてしまった。
筆者は、この話を聞いて、なぜヘシェルが精力的にユダヤ教の思想をわかりやすい言葉で著作にし、なぜ積極的にキリスト教との対話を進め、なぜ献身的ともいえるほど黒人の公民権擁護運動に参加し、なぜベトナム反戦運動を叫んだかが、少し理解できたように思った。
4. ハシディズムのたとえ
ヘシェルから与えられた研究用の図書一覧の中で、バアル・シェム・トブの最初の弟子になったヤコブ・ヨセフが著わした最初のハシディズム神学書『トルドット・ヤアコブ・ヨセフ』、バアル・シェム・トブの後継者ドブ・ベエルの語録『マギッド・デバラヴ・レヤアコブ』、その弟子レヴィ・イツハクの著書『ケドゥシャット・レビ』、ゼエヴ・ヴォルフの著書『オール・ハメイール』、レゼンスクのレベ、エリメレッフの著書『ノアム・エリメレッフ』、その弟子、コツク・レベのメナヘム・メンデルの語録『エメット・ヴエムナー』は、特に丁寧に読むようにと筆者は指示されていた。その他、バアル・シェム・トブの語録『リクティム・イェカリム』、その孫チェリンのナフマンが編集した『デゲル・マハネ・エフライム』などもリストにあった。これらは、いずれもハシディズム思想を学ぶ上で重要な基礎資料である。
レベたちの著述は、ふつうトーラー(モーセ五書)の註解という形式をとっている。トーラーの字句を註解しながら、そのじつ自分たちハシディズムの主張を述べている点で、彼等の著作は註解というよりもおおむね説法、ミドラシュである。いずれも、バアル・シェム・トヴやハマギッドの語録の引用が豊富な点で、初期のハシディズム運動を知るのに役立った。『エメット・ヴエムナー』は、ヘシェルに大きな影響をあたえたコツク・レベ、メナヘム・メンデル(1787-1859)の思想の理解に役立つ。
ところで、レベたちの説法には、しばしば比喩が用いられる。わりと頻繁に使われる比喩が、王と王子のたとえである。その一つに次のたとえがある。
* * * * *
王が、失った宝を見つけるために他国に王子を遣わした。王子は、素性が露見しないようにと、衣服を替えなければならなかった。彼は変装して出かけ、宝を無事に王に届けた。(異国で父王を恋しく思い出し慕った)この経験の結果、彼は以前にもまして父王に忠勤を励むようになった(4)。
* * * * *
ハシディズムの思想にはルリア学派カバラーの影響が濃い。カバラーでは、世界は神から流出する神聖な力によって支えられていると考えていた。だがもし世界が神の力だけによって支えられているのであれば、世界は整然と秩序ある善の世界であるはずだ。しかし現実には善と悪との葛藤がある。それは何故か。
ルリア学派によれば、宇宙創造の原初に、神から流出する神聖力を地上世界に伝える途中の受け皿が壊れ、神聖力の破片が火花となって世界に飛び散ってしまい、世界の秩序が破壊したからだという。しかも神の火花は世界の底部の暗黒の世界、つまり悪の中に取り込まれ、そのことが悪の力の動力となったとルリア学派は考えた。
この考えを受けてハシディズムは、人間は善行と礼拝を通してその飛び散った神の火花を回収し上界に戻す任務を担わなければならないと教え始めた。
上記の比喩における王子は、敬虔なユダヤ人のたとえである。失われた宝とは、地の果てまで飛び散った神の火花である。火花の回収という聖なる任務を果たすために、王子は世俗の人々の姿に変装し、神と密着している瞑想という王宮から脱出し、世俗という僻地へ行かなければならない。
ヘシェルが18歳のときに、ワルシャワのハシディズム社会からまずヴィルヌスの世俗社会へと一歩を踏み出したのは、自分が任務に耐え得るかどうか試したかったことも動機の一つであったと、筆者は推察する。ハシディズムの聖服に身を包んで、自分だけ穢れのない生活をすることに、彼は疑問をいだいていた形跡がある。それには、彼より4歳年長の兄ヤコブが、当時シオニズムをめざしていたことの影響もあったかもしれない。
ほとんど無一文でヴィルヌスに出、その後ベルリン大学に進んだものの、米国で定職を得るまで、自分はいつも生活に苦労していた、とヘシェルは筆者に語っていた。
ベルリン大学時代には、ユダヤ教徒としてのアイデンティティを喪失しかける危機もあった。その時の情況をヘシェル自身が著書に詳しく述べている(5)。 フランツ・ローゼンツヴァイクが大贖罪日の祈りの声でユダヤ教に立ち帰ったように、ヘシェルも西欧文化に呑み込まれる寸前にユダヤ教に目覚めなおした。
その時の経験を回想して、1971年秋のJTSのゼミ「ハシディズム」の講義のおりに、彼は「まるで遠い国からわが家に帰ったような新鮮な感情でユダヤ教を再発見した」と語っていた。この発言は上に紹介した王子物語の結末と一致する。
神の火花を上界に戻すことはユダヤ人の高貴な使命である。レベたちの説法によれば、そのために賢人は誘惑と穢れに満ちた世俗世界に下りて、人々と交わり、彼等の心をトーラーに近づけ、神に近づけなければならないと力説してある。たとえば、バアル・シェム・トヴの最初の弟子ヤコブ・ヨセフは次のように述べている。
賢人(タルミッド.ハハム)はときどき大衆の段階まで下らねばならない。彼は神との結合の段階を離れ大衆の段階へ下り、創造主の完全さを欠いた人々への人類愛を実践しなければならない。これは創造主を愛することにかない、彼等をトーラーに近づけるためである(6)。
どのようにして彼等を天の父に結びつけるか。それには、神への密着という聖なる衣服を脱ぎ、彼等と一緒になるために劣った衣服をまとう。その後、トーラーの定めや教訓を語ると彼等の心に入る。こうして彼等は天の父と結ばれ、近づくのである(7)。
HUCやJTSがユダヤ教の学院であるとはいえ、ハシディズムの基準からみると、それらは世俗世界であった。1945年HUCからJTSへ移るさい、正統派のイシバー大学からも誘いがあったが、ヘシェルはJTSを選んだ。ヘシェルの死後、シルビア夫人から直接聞いた話によると、第一に、保守派のJTSのほうがユダヤ教の伝統を守りつつ、それでいてユダヤ人の大衆への教化に熱心であったからである。第二に、JTSには、ルイス・フィンケルスティン、ルイス・ギンズバーグなどレベルの高い学者がそろっていたからである。
ヘシェルは、外面的にことさらにユダヤ教ぶることを嫌い、淡々と平服のまま人々と交わることができることを是としていた。
急死された前日、1972年12月22日の午後、ヘシェルを自宅まで見送っていく途中、彼が筆者に語ったことばには、世界の問題を少しでも解決しようとする彼の苦悩がにじみ出ていた。「研究室のなかで著述にふけっているときは、わたしは我をわすれ、神の圧倒する臨在におおわれている。しかし、この部屋を出るやいなや、わたしを取り巻く世界の重荷に耐えきれないのを感じる。なんと悲劇に満ちた世界だ。どうすればいいのだ…」(8)
5. ヘシェルの思想とハシディズム
5-1. A leap of action
ヘシェルは自己の思想形成においても、ハシディズムの思想から多大なヒントを得ている。
たとえば、彼が重視していた行動の重要性という概念は、ハシディズムの思想を現代的に発展させたものである。
ヘシェルによれば、「ユダヤ人は、思想の跳躍よりもむしろ行為の跳躍(a leap of action)を求められている。彼は自分のもろもろの行動 (his deeds)を凌駕することを、彼の理解を超えてより多く実践することを、求められている。それは彼が実践する以上のことを悟るためである。トーラーのことばを実践することのうちに、彼は霊的意味の実存へと招き入れられるのである。(トーラーを実践する)行動の歓喜を通して神の身近さが確かなことを知る」(9)
ここでヘシェルがいう「行動 deeds」とは、ユダヤ教が命じるさまざまの実践行為である。それは宗教的戒律にとどまらず社会的実践をも含む。むしろ社会的実践を通して、人は神の意志を成就することが出来るという考えである。
これについて、バアル・シェム・トヴの後継者となったハマギッドは次のように述べている。
上界からの神聖力の放射は、これを受ける器がなければ不可能である。というのは、至高の神聖さは非常に輝き光っているから、人はこれに耐えられない。マアセイ・ミツヴォット(戒律の実践)という受容器によってであれば、人はこれに耐えるし、受けとめることができる。戒律の実践はその内に最高の光りを秘めているからである(10)。
世界を支える神聖力は今も神から流出している。人はこれを世界のために適正に運用しなければならない。その高エネルギーを適切に制御し、世界に役立てる行為はミツヴォットの実践なのである。
ユダヤ教でいうミツヴォットはふつう戒律と訳されているが、正確には神の命令の意味であり、それは正義の実践や人命救助といった広範囲の人道的行為をも含む。
ヘシェルが「deeds」と複数形を用いたのは、彼の念頭に「マアセイ・ミツヴォット(the deeds of the Commandments)」というユダヤ教独自の概念が想起されていたからである。彼が日常的にミツヴォット、あるいはその単数形「ミツヴァー」ということばを使うときは、たいてい後者の意味で使っていた。
「実践する以上のことを悟る」というのは、実践を通して人は神とのつながりに気付き、神から流出する力を感じ、世界の秩序維持に参画するという使命を自覚するようになるとの意味であった。
5-2. The ineffable & awe
神の存在を身近かに感じる体験を、ヘシェルは「言い難い知覚(the sense of the ineffable)(11)と表現した。これはルドルフ・オットーのいう「聖なるもの」に遭遇する経験であり、人の心中にmysterium tremendum の感情を引き起こす(12)。ヘシェル流にいえば、「言い難い知覚は我々を好奇心よりもむしろ畏怖で満たす」(13)のである。
しかしながら、ヘシェルにおいては、言い難い知覚とはじつは畏怖の経験に他ならない。彼は一方で「畏怖は超越界への知覚である」(14)と定義し、他方で「言い難い知覚は超越界への知覚である」(15)と定義しているからである。
なぜ彼が二つの用語を使い分けたのか、その理由は定かでない。察するに、「言い難い知覚」は宗教経験に馴染んでいない人々への用語であり、「畏怖」は既に宗教経験がある人々への用語という配慮があったものと、筆者は憶測する。
彼は「畏怖は信仰に先立ち、信仰の根源にある。我々は信仰に到達するために畏怖によって成長しなければならぬ」(16)と、畏怖の重要性を強調する。
そのさい恐怖と畏怖を厳密に区別している。「恐怖は、悪もしくは苦への予想と期待であり、善への予想である希望と対照的である。畏怖は、一方、驚異の感覚、崇高なものによって触発された、または神秘に直面して感じる謙遜である」(17)
「信仰よりもむしろ畏怖が敬虔なユダヤ人の基本的態度なのである」(18)というヘシェルの発言も、じつはハシディズムから継承したものである。
「知恵の初めは神への畏怖である」と箴言(1:7)は宣言しているが、畏怖そのものについて殊更に論じることはミシュナ・タルムードでもあまり例がない。16世紀のユダヤ敬虔主義においても、畏怖は神の偉大さを観照した結果得られる境地であって、礼拝の前提条件ではなかった。初期のハシディズム文献を見ても、畏怖は「イルアー・ヴアハバー(畏怖と愛)」と終始、愛と一対で使われていた。第4世代の19世紀前半のハシディズム著作や語録になってはじめて、「イルアー・ヴアボダット・ハシェム(畏怖と礼拝)」という用語が日常的に使われはじめ、畏怖は礼拝の必須条件として取り上げられるようになる。
ヘシェルの父方の祖先、アプト・レベであった初代アブラハム・ヨシュア・ヘシェルは次のように教えている。
畏怖はすべての力と徳を守る手段であり、これ無くしては穢れと滅亡に至る。天への畏怖を持たない人は彼の一切の知恵も知性も、すべての力も徳も消滅し、無に帰してしまう.... 神への畏怖に心を打たれた者は、もろもろのミツヴァーを行う前に、恐れ畏みつつ天の支配のくびきを拝受する(19)。
畏怖なき礼拝は形式主義であり、神への畏怖を感じる者はおのずと礼拝をするものだと、レベたちは畏怖の宗教的意義を強調しはじめた。ヘシェルが、一般の読者にむかって畏怖の重要性を語るのは、まさしくこうしたレベたちの大衆教導の継承なのである。その証拠に、ラビ神学を取り上げた彼の大著『トーラ・ミン・ハシャマイム』のなかでは、わざわざ畏怖を取り上げ論じることさえしていない。
5-3. The Kotzk Rebbe
「知恵に至る唯一の道がある。畏怖だ」とヘシェルは宣言する。では、どのようにして畏怖に至ればいいのか。この疑問に対して、彼は一見不可解な回答をする。「あなたがたの畏怖をかなぐり捨てよ、あなたがたの自負心をして(神を)畏怖する能力を減少させよ、そうすれば宇宙があなたがたにとって町の広場となる」(20)
一方では畏怖の意義を説きながら、一方で畏怖心を持つなという。別の箇所では、「神秘の知覚は我々の意志の所産ではない」(21)と断わっている。つまり、畏怖は神の超越性に直面したとき感じるものではあるが、感じようと意図的に意識することではないのだ。
筆者の浅学な範囲で接したハシディズム文献のなかで、ヘシェルのこの考えを示唆する記述はコツク・レベの語録『エメット・ヴエムナー』でしか見い出せなかった。
我らのラビ(コツク・レベ)があるハシードに狼を見たことがあるかと尋ねた。彼は見たことがあると答えた。またラビが尋ねた。「狼を見て恐ろしかったかね」「はい、恐ろしかったです」 さらにラビが尋ねた。「恐ろしかった時に、自分に恐れがあると自覚したかね」その男はラビに答えた、「いいえ、恐ろしくて何も覚えていません」 そこで我らのラビは彼にむかって、「まさしく、そういうふうに天への畏怖をもつべきなのだよ。聖なる御方の前で怖れ畏み礼拝する時に、自分に畏怖があると感じてはいけないのだよ」(22)。
宗教的示威行為や人為的狂躁を戒める記述は、ヤアコブ・ヨセフの著書『トルドット・ヤアコブ・ヨセフ』、ルヴァヴィッチ派ハシディズムの2代目のレベ、ドブ・ベエル・シュネルソンの著書『タニア』などに散見される。しかし畏怖の在り方について言及しているのはコツク・レベだけである。
6. ヘシェルとハシディズム
ハシディズムやカバラの世界を西欧に紹介した点で、マルチン・ブーバーとゲルショム・ショーレムの功績は大きい。しかしながら二人ともハシディズムの観察者ではあったが、ハシディズム社会の成員ではなかった。ブーバーは、ブーバーの目から見たハシディズムを描いた。ショーレムはショーレムが描いたハシディズムを分析した。
ヘシェルはハシディズムの中に生まれ育ち、ハシディズムのハートを持ち続けながら、彼の頭上に響く永遠のこだまを世界に問いかけた。
ヘシェルの絶筆となった『A Passion for Truth』の冒頭でも、その前に書き上げたイディシュ語の著作『コツク』でも、「わたしの心は(バアル・シェム・トヴの住処)メズビズにあり、わたしの頭脳は(メナヘム・メンデルの住処)コツクにある」と述懐している(23)。ハシディズム世界の豊かな感性と鍛え抜かれた知性、その両極の緊張のなかでヘシェルは65年間の生涯を送った。
ちなみに彼の姓はヘッシェルではなく、「ヘシェル」となめらかに発音するのが正しい。
Heschel & Teshima, 1971
Notes:
(1) バアル・シェム・トヴを「良き名の師」と訳す例が多いが、バアル・シェムというのは護符師の職業名である。ラビ・イスラエルの書いた護符が霊験あらたかであったために、良きバアル・シェムと呼ばれるようになった。
参照:拙著、Zen Buddhism and Hasidism (Lanham, 1995), p.5.
(2) Edward K. Kaplan & Samuel H. Dresner, Abraham Joshua Heschel, (New Haven, 1998). 当初ドレズネルがヘシェル伝の編集を始めたが、資料収集など困難をきわめ、結局カプランが引き継いだ。本書は事実上カプランの執筆である。近く続巻が出る予定。
(3) 拙稿、"My Teacher," No Religion Is an Island, ed.、 Harold Kasimow & Byron L. Sherwin (Maryknoll, 1991) pp.63-67.
(4) Meshullam Phoebus,ed., Liqqutim Yeqarim, (Jerusalem, 1974), folio 63b, sec. 213.
(5) Abraham Joshua Heschel, Man's Quest for God, (New York, 1954), pp. 96-98.
(6) Ya'akov Yoseph Hacohen of Plonnoye, Toledoth Ya'akov Yoseph (Jerusalem, 1973), vol. 1, p.197.
(7) Ibid., p. 199.
(8) 拙稿、"My Memory of Professor Abraham Joshua Heschel," CONSERVATIVE JUDAISM 28 (Fall 1973), pp.78-80.
(9) Abraham Joshua Heschel, God in Search of Man, (New York, 1955), p. 283.
(10) Levi Isaac of Berdichev, ed., MaggidDevarav Le-Ya'akov by Dov Baer of Mezhirich (Jerusalem, 1971), folio 97b, sec. 267.
(11) God in Search of Man, pp.104f.
(12) ルドルフ.オットー著、『聖なるもの』、岩波文庫、p.16 & p.24.
(13) God in Search of Man, p. 105.
(14) Ibid., p. 75.
(15) Ibid., p.105.
(16) Ibid., p. 77.
(17) Ibid., p. 77
(18) Ibid., p. 77
(19) Meshullam Zusya of Zinkov, ed., Ohev Israel by Abraham Joshua Heschel of Apt (Jerusalem, 1962), p. 258.
(20) God in Search of Man, p. 78.
(21) Abraham Joshua Heschel, Man Is Not Alone (New York, 1951) p. 27.
(22) Israel Yaakov & Mordecai Arten, ed., Emeth Ve-Emunah by Menahem Mendel of Kotzk (Jerusalem, 1969), p. 52. See also p.84.
(23) Abraham Joshua Heschel, A Passion for Truth (New York, 1973) pp.xiii-xv; Abraham Joshua Heschel, Kotzk, 2 vols., (Tel-Aviv, 1973) p.10.
(本小論は、日本イスラエル文化研究会機関誌『ユダヤ・イスラエル研究』第18号(2001年3月)に掲載したものです)